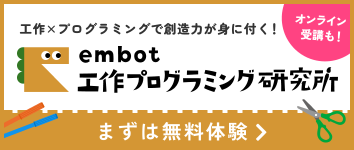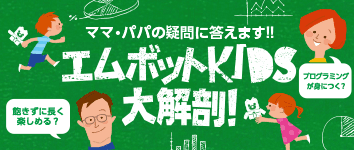【Master Nuコラム③】生成AIってどんなことができるの?
いきなりネタバラシ!

embot大展覧会も開催される夏が迫ってきており、バタバタ状態の中、コラムを書く担当が回ってきてしまいました。
なので、思い切って、AI大先生にゴーストライターを頼むことにしました!!
画像はWhiskというツールで作成し、文章はNotebookLMというツールで作成してみます!
※この段落は文章はNuが書いていますが、画像はWhiskです。
では、早速、次の段落からはAIにお任せコラムです!
過去のコラムと見比べてみると面白いかも!
ここからAIが作成したコラムです!

Master Nuです!キングじゃないよ、マスターだよ!
Master Nuコラム、第3回のテーマは、embotがなぜ「遊ぶほど、プログラミングが楽しくなる」のか、その根底にある「つくる楽しさ」と「感情」について深く掘り下げていきたいと思います。前回のコラムでは、embotの名前の由来が「Emotion Robot」から来ていることや、私がプログラミングを始めた頃の苦い経験から、「プログラミング”を”学ぶ」のではなく「プログラミング”で”学ぶ」ことの重要性についてお話ししました。
embotの原点:感情を伝えるロボットから創造の道具へ

実は、embotは最初からプログラミング教材として生まれたわけではありませんでした。趣味で開発を始めた当初は、置き時計や壁掛けカレンダーのように「単純だけど大切な情報を教えてくれる」ロボット、つまり「Emotion Robot(感情お届けロボット)」として構想されていたのです。私の携帯電話が通知だらけになり、大切な連絡が埋もれてしまう経験から、「ふとした時に確認したい大切な情報は、遠くにいる大切な人の感情なのでは!?」という仮説が生まれ、感情を伝達するロボットを作ろうとしたのが始まりです。
この感情を伝えるというコンセプトで開発されたembotが様々なコンテストで評価を得て、子ども向けのイベントに展示した際に、子どもたちから「自分でもつくってみたい!」という声が上がったことが転機となりました。この「作ってみたい」という純粋な好奇心が、embotをプログラミング教材へと進化させるきっかけとなったのです。
「プログラミング”で”学ぶ」ことの真髄

前回のコラムでもお伝えしましたが、私がプログラミングを学び始めた頃は、高価なPCや複雑な環境構築に苦労しました。しかし、多くの優れたプログラマーに話を聞くと、彼らのプログラミングのきっかけは「つくりたいものをつくるため」だったのです。
embotは、この「つくりたいものをいきなりつくれる!」というコンセプトを大切にしています。プログラミングはあくまで「つくるため」のツールであり、ツールを習得すること自体が目的ではないのです。
embotは、身近な素材であるダンボールと電子工作パーツを用いてロボットを組み立て、専用アプリでプログラミングすることで、子どもたちが「作りたい」「動かしてみたい」という想いを形にできる体験を提供します。組み立ては、くり抜き、折り、差し込むといった簡単な工程で、紙コップや空き箱なども使って自由にカスタマイズが可能です。
アプリは直感的に操作できるブロック式とフローチャート式のインターフェースを備え、子どもの習熟度に合わせて5段階のプログラミングレベルが設定されています。これにより、初めてプログラミングに触れる子どもから経験者まで、それぞれのレベルで楽しめます。
この「ものづくり」と「プログラミング」の組み合わせが、子どもたちの発想力、創造力、課題発見・解決能力、非認知能力を育みます。思いついたアイデアを形にし、何度も試行錯誤しながら工夫して遊ぶことで、創造的思考力が身につくのです。
NTTドコモの新規事業創出プログラムから生まれたサービスであるembotは、社内ベンチャー制度を利用し、e-Craft社によって企画・開発・販売が行われています。また、タカラトミーが製造・販売を担っています。
遊びが学び、学びが創造へ

私がembotを通じて目指しているのは、「プログラミングに対する価値観の変容」です。プログラミングは難しい、オタク的という固定概念を壊し、「足の速い子だけでなく、プログラミングできる子もモテる」ような世界を実現したいと考えています。
子どもたちが自らサービスを提供するプラットフォームを構築することが、e-Craft社設立当初からの構想でもあります。実際に、embot大展覧会のようなイベントでは、子どもたちが出展者として自ら作品をプレゼンし、他の参加者や審査員が投票することで、その創造性が認められ、自己実現の機会となっています。
embotのシンプルなダンボールデザインは、子どもたちに感情移入させ、愛着を抱かせます。プログラミングのコードを書く楽しさだけでなく、「embotを次はどう動かそうか」というembotとのコミュニケーションを楽しみながら、プログラミングを学んでほしいと願っています。
未来の社会では、AIやIoTなどの技術がさらに進化し、ツールがどんどん「つくりやすい世の中」になっていくでしょう。だからこそ、プログラミングという「ツールを習得する」意識から、「プログラミングを使ってどのようなものがつくれるか」という「創造する」意識に変えていくことが、これからの子どもたちには何よりも重要だと信じています。
これからも、embotが子どもたちの無限のアイデアを形にする手助けとなり、彼らが未来のコミュニケーションや社会を創造していく力となるよう、遊びながら、創造し続けていきたいと思います!
皆さんのembotでの素晴らしい作品、ぜひ「embot図鑑」に投稿してくださいね!
では次のMaster Nuコラムでお会いしましょう!